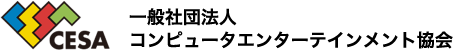ゲーム研究者インタビュー
養老 孟司先生インタビュー【第1回】
テレビゲームへの正しい理解を~ゲーム研究者インタビュー
養老 孟司先生インタビュー

養老 孟司(ようろう・たけし)
東京大学名誉教授/解剖学者
1937年、鎌倉市生まれ。解剖学者。東京大学名誉教授。趣味は昆虫採集。テレビゲーム好きとしても知られる。1989年、『からだの見方』でサントリー学芸賞受賞。2003年、『バカの壁』で毎日出版文化特別賞受賞。東京国際マンガミュージアム館長、日本ゲーム大賞選考委員会委員長。『唯脳論』『解剖学教室へようこそ』『死の壁』など著書多数。
第1回テレビゲームと脳と文化
2007年10月25日掲載
-
脳はマルチチャンネル
- ――養老先生がテレビゲームをお好きなことは有名ですが、どんなときにゲームをされますか。
養老:僕が日常の中でテレビゲームをするのは、気分を変えるときですね。散歩に出かけたり、虫を捕りに行ったりするのも大きな気分転換だけども、それができない場合があるでしょう。そういう時にゲームをします。例えば、原稿の合間に人が来たりすると気が散ってしまう。原稿に戻る前にしばらくゲームをして、気持ちを切り替えたりします。でも集中してしまうたちなので、ゲームも始めると、気がついたら「あっ、いつの間にかこんな時間」ということもありますね。
- ――それだけ熱中してしまうと、気分を変えるというより、かえって頭が疲れてしまうように思うのですが。
養老:原稿を書くのとゲームをするのでは、脳の使っている部分が違うのだと思います。一つのことをずっとやっていると、バランスが崩れてくる。それをゲームによって脳の違う部分を使うことによって、バランスを取り戻しているのだと思います。
- ――子どももテレビゲームに夢中になりますね。脳への影響を危惧する意見もありますが。
養老:人間の脳はそう単純なものではありません。同じことをするにしても、人によって違う回路を使っていることもあります。アメリカの物理学者ファインマンの本(『困ります、ファインマンさん』)にありますが、「声を出さずに数を数える」実験をすると、普通の人は声帯を使ってはいないけど、実は暗黙のうちに声を使って「1、2、3、4」と数える。ところが人によっては、日めくりカレンダーをめくるように、次々に目を使って数えている人もいる。そういう人は、数を数えながら、おしゃべりができる。しかし、暗黙の声で数を数える人はおしゃべりができない。でも、同時に本は読める。つまり使っている場所のチャンネルが違うから、そういうことが可能なのです。人間の脳は思っている以上にマルチチャンネルです。だから、ゲームに夢中になりすぎると危険だという意見もありますが、どのような影響があるのかは長期的実証的な研究を続けてほしいと思います。
ただ、子どもがゲームだけをやっている状況はおかしいと、僕も思います。今みたいに子どもがゲームを持ち寄って集まって、一人一人別々のゲームをやっているのは正常な状態ではないし、室内にいる時間が長いのは好ましいことではありません。テレビゲームとどうつきあっていくか、また、テレビゲーム以外の世界をどう広げているか、つきあい方をもっと成熟させていくべきでしょう
文化は人を虜(とりこ)にする- ――テレビゲームの普及は、脳の世界とも関わりがあるのでしょうか。
養老:これはかなり微妙な話題です。テレビゲームには集団催眠、麻薬効果があると批判している本がありますが、なぜこうまでに広まったのか、まだまだ考えるべき部分はあると思います。先ず考えてほしいのは、時代をさかのぼってみると、その時その時で人々を夢中にさせるものがあって、「それはいけないものだ」といって叩くことを人は繰り返してきました。
例えば、江戸時代後期の農政家・二宮尊徳。ある世代から上の人は、少年の尊徳が背中に薪を背負って本を読んでいる銅像がどこの小学校にもあったことを覚えているでしょう。あれは本を読むことを賞賛していたわけです。しかし、二宮尊徳自身はおじさんの家に預けられ、夜、行灯の明かりで本を読んでいると、「油の無駄だ」と怒られていた。「本を読むような余計なことをやっている閑はない。一生懸命働け」と言われていた。にもかかわらず、二宮尊徳は本を読むのです。
読書にも中毒性があります。それはなくても生きていく上では困らない。でも、夢中になってしまう。そういうものは、どの時代にもなにかしらあります。僕は文化というのは、そういう麻薬効果的なところから生じたものではないかと思います。
さらに言えば、読書は今や当たり前のことで、「ダメだ」とは言われません。
「脳化」社会は体を軽んじる- ――過去にはテレビにもいろいろな批判がありました。
養老:テレビが普及していったときに、ジャーナリスト大宅壮一は「一億総白痴化」と言いました。でも、僕は逆になったと思います。「一億総インテリ化」。テレビが当たり前のものになってから、昔、言われていたインテリの欠点のほうが、社会の表面に出てきてしまったと感じています。つまり、体を使っていない。体を使って働くことをバカにする傾向は強くなっています。僕はそのことがむしろ心配です。
世界的に見ても、体を使って働くことに対して、価値をもたせる文化は非常に少ないのです。西洋文化はその典型で、民主主義の歴史をさかのぼっていくと、ギリシアのアテネにたどりつきます。アテネは10万の奴隷と10万の市民でできていた。10万の奴隷が体を使って働く部分を担当していましたが、奴隷は民主政治に参加できない。つまり、体の部分が切り捨てられているんですね。貴族制度もそうです。立場が高くなると、体を使って働くことをしない。その代わり、ヨーロッパの貴族は体の部分はスポーツという形でになわせました。でも、それは本来の体の使い方ではない。
元来、文化とは体を軽んじているのです。私たちが生きている社会は頭に重きを置いた「脳化」した社会で、体を無視しているために非常にバランスが悪い。それでも、私たちはこの社会の中で、まともに生きていかなければならない。非常にやっかいだと思います。
- ――テレビゲームもそういう中で登場したものなのですね。
養老:コンピュータを使っていくと、テレビゲームのようなものは必然的に発生してくると思います。
昔から分別(ふんべつ)という言葉があります。「分」も「別」もどちらも「わける」という意味を持っています。「大人になって分別がつく」と言うけれど、人間が年を取るということは、だんだん世の中のいろいろなことを自分の中できちんと仕分けできていくということです。テレビゲームについて言えば、今は社会全体で仕分けができていない「分別がついていない」状態だと思います。